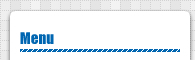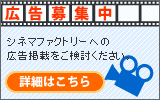『ONLY SILVER FISH –WATER TANK OF MARY'S ROOM』
オフィシャル・インタビュー
2018-11-25 更新
西田大輔監督
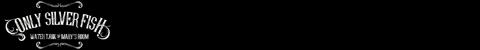

© 2018「ONLY SILVER FISH」製作委員会
配給:ベストブレーン
![]()
西田大輔監督
1976年11月13日生まれ。東京出身。
1996年、AND ENDLESSを結成。同劇団主宰。旗揚げ以来AND ENDLESSの作品全ての作・演出を手掛ける。
1999年、日本大学芸術学部演劇学科を卒業。
2000年、日本の若手劇団から東京代表として選ばれ、フィジカルシアターフェステイバルに参加、韓国・ソウルオープンシアターで「楽園」を上演。好評を得る。
2003年、演出家としては26歳の史上最年少で新宿・紀伊國屋サザンシアターで公演。
2004年、紀伊國屋ホールにて「FANTASISTA」(作・演出・主演)を上演。
2005年、初の戯曲本「FANTASISITA」を出版(論創社より)。以来、年一冊のペースで出版を続ける。
2006年、旗揚げ10周年記念公演「美しの水」(作・演出・主演)にて追加公演としてシアターアプルにて公演。
2015年、DisGOONieを設立。DisGOONie代表 旗揚げ記念公演「From Chester Copperpot」3作同時上演を果たす。
現在、ドラマ脚本や漫画の原作依頼などに加え、演劇界に限らず作家・演出家としての知名度も広がっている。
![]()
ある古い洋館に集められた男女たち。屋敷の中に置かれた大きな水槽。その中にはONLY SILVER FISHと呼ばれる魚がいる。そして彼らが手にする招待状には、謎めいた言葉が……。極上のサスペンス・ミステリー映画『ONLY SILVER FISH –WATER TANK OF MARY'S ROOM』。11月24日(土)より公開が始まった本作で映画監督デビューを飾った、舞台「煉獄に笑う」や「戦国BASARA」シリーズの人気舞台演出家・西田大輔のインタビューが到着した。
本作は西田さんの記念すべき初監督映画となりましたが、映画撮影に至った経緯を教えてください。
もともと、自分の物語を映像で表現したいという考えが漠然とあり、それを実現するチャンスを待っていたところに、「舞台と映画を同時に連動してやってみませんか?」というお話をいただいたのがきっかけです。舞台作品は原作物もあればオリジナルの物も作っていたので、映像の場所でもやるならばオリジナルのものでありたいという思いがありました。 この作品ならば自分のやりたい形で作れる可能性があるのではないかと思い、今回、作らせていただきました。
この物語の構想はいつ頃から練られていたのでしょうか?
舞台の『ONLY SILVER FISH』は2007年に発表した作品なので、「世界にたった一匹だけの魚がいて、その魚の本当の名前を呼ぶと過去を振り返れる」というコンセプトはその時からありました。同じコンセプトで新たな物語を作って映像に挑みました。
まるで舞台を観ているような臨場感と、あたかも自分があの場でゲームに参加しているような緊迫感があり、最後まで目が離せませんでした。冒頭からスピーディー展開が続くサスぺンス・ミステリーですが、監督ご自身はミステリーがお好きですか?
そうですね、ミステリーやひとつの場所で起こる密室劇に強く惹かれるものがあります。
謎めいた登場人物たちは、名前ではなく通称で呼ばれています。黒ネクタイの男、白ネクタイの男など、彼らを表すモチーフや衣装はすぐに浮かびましたか?
イメージはパっと浮かびました。一度に12人が映像に現れたら、名前を覚えるのも大変だし、見ている側も混乱するだろうなと。だったら名前なんて要らないんじゃないかというコンセプトがあるんです。『ONLY SILVER FISH』というタイトルとリンクさせたいという思いがあり、タイトルから彼らのモチーフを決めていきました。言葉、タイトルありきの登場人物です。物語は難解な構造をしているから、誰もが僕が書いたシナリオをもとにイメージできるわけじゃゃない。僕に迷いがあると「要は何なんだ、これは?」となってしまうので、ストーリーも含めて悩まず一気に作りあげました。
一斉に指をさして脱落者を決めていく緊迫した心理描写にハラハラしました。なぜ彼らがここに集まったのか、誰が生き残るのか、謎が謎を呼ぶストーリーですが、台本を読んだ時のキャストやスタッフの反応はいかがでしたか?
僕の中では台本をすごく細く書いたつもりでしたが、読んだスタッフたちは「分からなかった」と言っています(笑)。俳優たちはすごく繊細に考えて、ものを作るから「これはどういう意味ですか?」と聞かれることはたくさんありましたね。でも、考えなくていいことってあるんです。そういうのは「考えないで、やってくれ」と言いました。表現するのは俳優であり、その表現の仕方は俳優を信じないとできないものだから、僕が表現したいことは的確に伝えてあとは俳優を信じました。
なぜ、過去に“戻れる”ではなく、“振り返れる”という言葉にされたのでしょうか?
僕の中では、その時はまったく気にしていなかったけれど、「なぜ、あの時のあの人はあんな言葉を言ったのだろう?」「なぜ、あの時のあの人は寂しそうな顔をしていたのだろう?」と、ふと降りてくることがある気がしています。それは、過去を思い出すというよりも、 振り返ることだと思うんです。魚の本当の名前を知ったからといって、必ず過去を振り返れるという確証もない。さらに、「戻れる」という言葉じゃなくて「振り返れる」だから、 ただ思い出せるだけなのかもしれない。それでも彼らは、振り返りたい、取り戻したい何かがあって集い、この洋館に辿り着いた。その意味を込めて「戻れる」ではなく「振り返れる」にしました。
本作で西田監督がこだわった映像ならではの表現について教えてください。
僕の中でこの映画は挑戦状だと思っていて、パッと見て分かるような物語は絶対に嫌だったんです。一つの意味が視点を変えると違って見えるように、映像でしか見せられないものを作りたかった。それは世の中にないものであり、僕にしかできないものでありたい。お金持ちのおしゃれなジェントルマンとミセスが、ソファーに座ってくつろいで、上質なコーヒーや紅茶を飲みながら小説を読むという状況にはしたくないな、って(笑)。
優雅に観られるような作品にはしないぞ、と?
そう。観終わった後に「なんだ、この映画は?」と話題になるくらいがいいなと。人は極限の状態で初めてその人の本質が見えるような気がするので、それを描いた物語と、「お、なんだ?」と、観客がぐっと前に乗るような感覚が映像で表現できたら幸せだなというのはありましたね。
次々に変わる視点と暗闇がスリルを増し、この物語の世界観にどんどん引き込まれていきました。照明の光と色にもこだわりがあったそうですが。
編集作業で色をつけることもできると思うのですが、やはり、密室のこの空間の色はリアルでなければいけないという思いがあったので、水槽の色も、一つひとつのシーンの色も、細部までこだわって撮っています。ただ、映画の世界では照明をひとつ変えるのにこんなに時間がかかって大変なものなのかとびっくりしました。
舞台とは違いましたか?
舞台はいつも正面から見るものですが、映画の場合は、カットごとに撮る方向が変わり、どういうふうに光を当てるかによって、照明の位置もずれるし変わってくる。一つの色から一つの色に変わっていくさまも、丁寧に撮りたい画の色にするのはすごく時間がかかるんだなと思いました。撮影監督と話して照明を変えてもらったりしたのですが、「え? マジで照明変えるの? もうやめてくれ」みたいな空気はありましたね(笑)。
撮影現場で想像と違ったことや面白かったことはありますか?
初めての場所だからすべてが新鮮で面白かったです。僕らは舞台を作っていて、舞台はその瞬間瞬間が勝負なんです。毎回リセットされた後にもう一度同じステージがあって、それにどう向き合うか。その中で、僕は僕の物語と毎ステージ、リセットする俳優たちと日々の思考を重ねていく。それが舞台の作業なのですが、映画は撮ったら終わりだから、消えていっちゃう物語なんだなと思いました。
切ない気持ちになりましたか?
そうですね。舞台だと、その作品がすごく面白かったら、いつかもう一度この物語と巡り会う可能性はあると思いますが、映画だとなかなかそんな機会はないよなって。何十年も経ってリメイクするならともかく、同じ作品を撮り直したなんてないですよね。僕にとって、この物語と触れられるのは、この一回きりなんだなという思いがあります。
撮影を振り返って、撮影現場での思い出深いエピソードを教えてください。
一番よく覚えているのは、撮影の休憩時間に松田 凌と玉城裕規が二人で僕のところに来て、「監督、この映画は……、つまりは、どういう意味ですか?」と聞いてきたんです。よく一緒にものを作っている俳優たちでもあるから、僕がどういう心理でやろうとするのか、毎回探ろうとするんですよ。
彼らにどう答えたのですか?
「俺もお前らも世界という枠で見れば無名だ。まだ、誰も知らない。誰も知らないから作れる物語ってあるよな。俺は、日本だけじゃなくて、世界に旅するような映画を撮りたいんだよ」と言ったら、「あ、分かりました。じゃ」と言って帰っていった。それだけで伝わるというか、彼らとはそういうツーカー感がある。
一言、二言で分かりあえるような信頼関係がある?
あると思います。だから細かいことは考えない、という空気にはなりましたね。今回初めて一緒に作品を作る人もいましたが、このチームは「こういうことだから」と言って伝わる空気感がありました。ユキを演じた皆本麻帆さんには、「考えなくていい。悩んだ感情のままいてくれ。そこを切り取るのはこっちの仕事だから」という話はしました。
それぞれの表情が、物語の謎を解くヒントになるかもしれません。最後に、これからこの映画をご覧になる方へ監督からメッセージをお願いします。
始まりの場所というのはすごく素敵だなと思っていて、その始まりの場所を観客の皆さんと一緒に共有できるというのは、すごく上質な時間だと思います。「何を考えているのか分からないやつが何か始めたぞ。よし、じゃあ、いっちょ観てやるか!」という感じで観て欲しいなと思っています。できるならが、この作品はどこにもない物語でありたい。監督として僕でしか撮れないものでありたい。一つの新しい場所を一緒に共有して旅して欲しいなと思います。あとは本当に、「考えるな! 感じろ!」と。この物語を、まずは観て、感じていただきたいです。
この映画を監督からの挑戦状だと思って、多くの方に受け取っていただきたいですね。ちなみに、すでに次回作の構想を考えていらっしゃったりするのでしょうか?
もちろん考えています! 実はもう新しい物語を用意していて、それが実現するかはこの作品にかかっています。やりたいことがありすぎて困るくらい、新しい映像の世界の奥深さを感じていて、映像でしかできない新たな物語がある。もう早く撮りたい。だから、「神様頼みます!」と僕は思っています。この映画が失敗すると、もう次はないわけですから(笑)。皆さん、この映画をよろしくお願いします!
(インタビュー・文:出澤由美子、写真:笹原良太)
![]()
関連記事