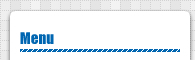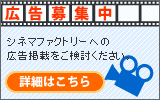『アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男』
ジャパンプレミア
2016-10-20 更新
ラース・クラウメ監督


配給:クロックワークス/アルバトロス・フィルム
2017年1月7日(土)、Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開
© 2015 zero one film / TERZ Film
![]()
長らく封印されていたナチス・ドイツ最重要人物アドルフ・アイヒマン拘束に関する<極秘作戦>の裏側の真実を濃密かつサスペンスフルなタッチで描ききり、ドイツ映画賞で作品賞、監督賞、脚本賞など最多6冠に輝いたほか、世界中の映画祭を席巻した映画『アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男』。
ドイツやヨーロッパ公開時に多くの動員を記録し、先頃公開されたアメリカ国内でも、ロサンゼルス・タイムズ紙が「映画全体に力を与えているのは、ベテラン・ドイツ人俳優ブルクハルト・クラウスナーの説得力ある演技だ。彼はバウアーの熱狂的な強烈さを正確に捉えている」と評した他、各紙がこぞって絶賛評を掲載するなどして話題となっているスリリングなサスペンス・ドラマだ。
この度、本作のメガホンを取ったドイツの気鋭、ラース・クラウメ監督が来日し、10月16日(日)・17日(月)に開催されたドイツ映画祭2016「HORIZONTE」でのジャパン・プレミアへ登壇し、Q&Aを行った。
ヴィクトリアのキャスティングについてお聞かせください。
ラース・クラウメ監督: 元々ヴィクトリア役は男性を考えていました、美しい男性俳優の候補が何名もいたのですが、どうしてもハイヒールを吐いた時に格好がつかなかったということと、当時の同性愛が許されない時代に、刑法175条で裁かれるという場の法廷にいるということは、見た目が女性としてパーフェクトでなければならないということもあり、リリスさんへお願いすることとなりました。現在は有名な女優さんですが、当時はまだ主演作がなく、今ほど有名ではなかったので、気がつく人は少なかったのではないかと思います。
フランスの方(共同脚本のオリヴィエ・グエズ)と一緒に仕事をされた理由は?
ラース・クラウメ監督: オリヴィエさんは作家で、2011年にドイツに戦後戻ってきたユダヤ人を書いた本を出されました。この本はなぜホロコーストのあとにドイツに戻ったユダヤ人がいたのかということに焦点をあてたもので、その中にバウアーのことも書いてありました。フランクフルトにいながら私はその本を読むまでフリッツ・バウアーを知りませんでした。
オリヴィエさんといろいろ話をする中で、一緒に映画を撮ろうということになり、最初はその本を題材にしようと考えていたのですが、段々フリッツ・バウアーという非常にエキサイティングなトピックに注目することとなって、彼を取り上げることで、50年代、60年代のドイツの過去との向き合い方に一番迫れるのではないかと思い、彼を主人公に据えることにしました。そして彼の長い人生の中でも、特にアイヒマンに関わる部分を更に切り取りました。オリヴィエさんにとっては初めて脚本を書くということになりましたが、彼自身もユダヤ系で、戦後に多くのユダヤ人の方へインタビューをされており、こういったことに非常に詳しい方です。
フリッツ・バウアー伝記を映画の公開にあわせ出版する予定なので、現在翻訳を進めています。ニュルンベルク裁判はあったとはいえ、ドイツで戦後ナチの人たちが生き延びて、法律の分野にもいたということに驚きました。監督もフランクフルトにいながら、フリッツ・バウアーを知らなかったというのもさらに驚いたのですが、『顔のないヒトラーたち』にもバウアーが出てきたり、『ハンナ・アーレント』へも話が続いていて、ヒトラーの死後70年経ち、ドイツの戦後処理について、ドイツの若い人たちは向き合わなければいけないという気持ちが強くなってきたのかと思ったのですが、ドイツ国内ではどうなのでしょうか?
ラース・クラウメ監督: 多くの人たちがアイヒマン拘束について決定的な役割をしたのはアメリカのサイモン・ヴィーゼンタールだと思っており、モサドがアイヒマンを拘束したということは知っているのですが、フリッツ・バウアーのおかげでアイヒマンを追跡することができ、裁判に至ったということは知られていませんでした。伝記が出る前というのは彼に関する本はなく、知られていなかったので、若い人にこの映画を観て知ってもらえたのなら嬉しく思います。今日の世界で起きているさまざまなことを考えると、民主主義のために、そして正義のために何が出来るのかということについていろいろとインスピレーションを与えてくれる映画だと、個人として思います。フリッツ・バウアーは一人で英雄のような戦いをしているわけで、彼が知られるようになり、こうして外国で上映されることに喜びを感じています。
監督がおっしゃった通り、個人として何が出来るのかということについてすごく勇気づけられる内容だと思います。フリッツ・バウアーがアンガーマンに向かって発した、“独裁の監視に屈してはならないのだ”という台詞がありましたが、あれは実際にフリッツ・バウアーが言った台詞なのか、脚本で作られた言葉なのか知りたいです。
ラース・クラウメ監督: 台詞そのものは脚本作家である私たちが生み出したものです。ただしそれはフリッツ・バウアーの思想から生み出したものです。例えば、テレビのトークショーに出演する場面がありましたが、そこではフリッツ・バウアーの肉声を使っています。ただ、実際にトークショーに出演したのは、劇中の時期ではなくて、あれから4年後のアウシュビッツ裁判の時期ですので、それは少し史実とは異なっています。ただ、私たちが大切にしたのは、彼が若い人たちに対してどう向き合っていたのか、彼のヒューマニズムがどう表れていたのかということです。最初のほうの場面で若い検事がフリッツ・バウアーの部屋に集められる場面がありましたよね。アンガーマンはフィクションですが、それ以外は実在の人物です。アンガーマンのように実際に同性愛が理由で脅された若い検事がいたということが史実としてありました。その辺りは時代的にアイヒマンの追跡の頃とは重ならないのですが、フィクションを交えて織り込んでいます。フリッツ・バウアーがどのような形で若い人に接したかということは徹底的にリサーチをしました。
 フリッツ・バウアーは一日18時間働き、チェーンスモーカーで、死ぬまで働いていた人です。何が彼をそこまで突き動かしているのかということをすごく知りたいと思いました。実際に彼は検事として華々しい成功を収めたかというと、決してそうではありません。アイヒマンもドイツで裁けませんでしたし、アウシュビッツ裁判でも願ったように全ての犯罪者を裁けたわけではありませんでした。それでも彼を動かしていたものは何なのか、推測に過ぎませんが、出所を条件に彼がナチスに従うということに署名してしまったことへの贖罪ではないか。復讐ではなく、やはり若い世代を教育したい、戦後のドイツの若い民主主義を育てたいというその気持が彼を突き動かしたのではないかと思います。それが、カール・アンガーマンへの台詞の言葉につながっています。
フリッツ・バウアーは一日18時間働き、チェーンスモーカーで、死ぬまで働いていた人です。何が彼をそこまで突き動かしているのかということをすごく知りたいと思いました。実際に彼は検事として華々しい成功を収めたかというと、決してそうではありません。アイヒマンもドイツで裁けませんでしたし、アウシュビッツ裁判でも願ったように全ての犯罪者を裁けたわけではありませんでした。それでも彼を動かしていたものは何なのか、推測に過ぎませんが、出所を条件に彼がナチスに従うということに署名してしまったことへの贖罪ではないか。復讐ではなく、やはり若い世代を教育したい、戦後のドイツの若い民主主義を育てたいというその気持が彼を突き動かしたのではないかと思います。それが、カール・アンガーマンへの台詞の言葉につながっています。
(オフィシャル素材提供)
![]()
関連記事